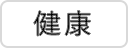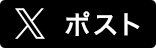寒さや乾燥が増す冬は、ウイルスや細菌の好む環境である一方、感染症に対する体の免疫力が落ちる季節でもあります。今回は、冬に多い呼吸器や消化器の感染症の予防、症状が出た際の対応についてご紹介します。
もくじ
1.冬に多い感染症
(1) 呼吸器の感染症
(2) 消化器の感染症
2.感染症を予防するために
(1) 呼吸器の感染症を予防するために
(2) 消化器の感染症を予防するために
3.症状が出た時の対策
(1) 発熱、咳、鼻水などの風邪症状の市販薬の選び方
(2) 下痢、嘔吐などの胃腸症状の市販薬の選び方
1.冬に多い感染症
冬は、寒さで体温が低下することで、体の免疫力が低下します。一方、寒さや乾燥を好むウイルスや細菌が増殖しやすいため、呼吸器や消化器などの感染症が増加しやすい季節です。
(1) 呼吸器の感染症
冬に多い呼吸器の感染症として、インフルエンザやマイコプラズマ肺炎が挙げられます。主な症状は、発熱や咳、のどの痛み、倦怠感など、一般的な風邪に見られる症状と共通しており、症状だけで判別するのは困難です。
(2) 消化器の感染症
冬に多い消化器の感染症として、ノロウイルス感染症が挙げられます。ノロウイルス感染症は、ウイルス性の胃腸炎であり、主な症状は嘔吐や下痢、発熱などで強い感染力があります。嘔吐や下痢などが続くと脱水症状を引き起こすこともあるため、特に、脱水症のリスクが高い小児や年配の方などは早めに医療機関を受診することが大切です。
呼吸器や消化器の感染症は日常生活に支障をきたす場合があります。まずは、感染症にかからないための予防が大切です。
2. 感染症を予防するために
感染症対策の基本は、ウイルスなどを体内に取り込まないようにすること、体内に入り込んだウイルスなどに負けない体の免疫力を維持することです。感染症の種類に応じた予防のポイントを確認していきましょう。


(1) 呼吸器の感染症を予防するために
まずは、ウイルスなどを体内に取り込まないようにするため、感染経路を断つことが大切です。呼吸器の感染症の主な感染経路は、「接触感染」と「飛沫感染」です。
「接触感染」とは、ウイルスなどが付着した手や物を介して、口、鼻、のどなどの粘膜から侵入する感染経路です。接触感染を防ぐためには、こまめな手洗いや消毒が効果的です。手洗いは、ハンドソープなどを使って泡を作り、20秒以上かけて、手のひらだけでなく爪や指の間、手首も丁寧に洗うようにしましょう。手指を消毒する場合は、速乾性があり、比較的殺菌効果が高い、消毒用アルコールが適しています。キッチンやトイレを消毒する場合は、より殺菌効果が高い、次亜塩素酸ナトリウムを利用すると良いでしょう。
一方、「飛沫感染」は、ウイルスなどを含む飛沫が咳やくしゃみの際に飛散し、この飛沫を介して侵入する感染経路です。冬は空気が乾燥しているため、飛沫に含まれる水分が蒸発して、飛沫が小さく軽くなり、遠くまで飛びやすくなります。そのため、マスク着用や部屋の換気が重要な予防策となります。ウイルスは寒さや乾燥を好むため室内環境は、温度22~25℃、湿度50~60%を目安に調節するようにすると良いでしょう。
また、体の免疫力を維持し続けることも大切です。免疫力を維持するためには、十分な睡眠が欠かせません。成人の場合は、目安として、毎日6時間以上の睡眠をとることを心がけましょう。また、栄養バランスの取れた食事も重要です。水分を十分に摂り、体を作る主な材料であるたんぱく質、鼻などの粘膜保護に関連するビタミンA、体の免疫力に関連するビタミンCを豊富に含む食事を心がけましょう。


なお、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症には予防接種があります。流行が始まる前にワクチンを接種することで、感染リスクを低減することが出来ます。特に年配の方や基礎疾患を持つ方は、重症化を避けるために、ワクチン接種を検討してみてはいかがでしょうか。
(2) 消化器の感染症を予防するために
ノロウイルスによる胃腸炎は、ウイルスに汚染されたカキなどの二枚貝を、生で、あるいはよく加熱せずに食べた場合に感染します。これを「経口感染」といいます。そのため、カキなどの二枚貝を生で食べる場合は、「生食可」と記載されているものを選びましょう。加熱調理が必要なものは、中心温度85℃以上で60秒以上加熱しましょう。
また、調理者や配膳者が感染していて、ノロウイルスに汚染された手指で食材に触れ、その食材を食べることでも感染します。ノロウイルスはごく少量が体内に入るだけでも感染するため、調理する前には、良く手を洗うことを心がけましょう。なお、ノロウイルスで汚染された調理器具等の消毒には、殺菌力の強い次亜塩素酸ナトリウムが適しています。
3. 症状が出た時の対策
高熱(40℃以上)が出ている場合、咳・たん・下痢・嘔吐が長く続く場合、また、発症すると重症化しやすいといわれる、ぜんそく・糖尿病・心臓病などの基礎疾患を持つ方は、早めに医療機関に相談しましょう。発熱・咳・鼻水・下痢・嘔吐などの症状があり、インフルエンザやノロウイルス感染症などにかかっている可能性が低い場合は、それぞれの症状に合わせた市販薬を利用すると良いでしょう。。
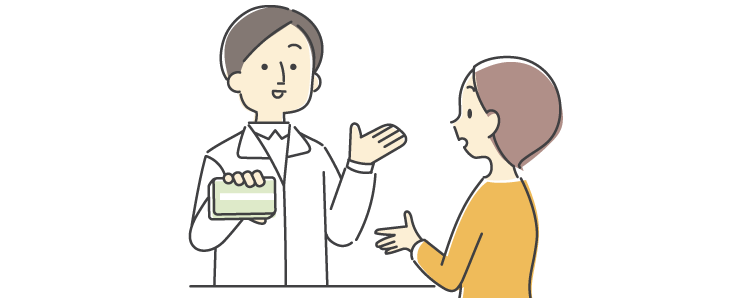

(1) 発熱、咳、鼻水などの風邪症状の市販薬の選び方
風邪症状の市販薬を選ぶポイントとして、症状が出始めた時期、症状が複数出ているかが一つの基準になります。風邪の引き始めで寒気がある時は、体を温めて発汗を促す「葛根湯」が効果的です。複数の症状がある場合は、総合感冒薬を利用すると良いでしょう。症状が1つだけの場合は解熱鎮痛薬や咳止め、鼻炎薬、去たん薬など、症状に特化した市販薬を選びましょう。
発熱や頭痛には「イブプロフェン」や「ロキソプロフェン」が配合された市販薬を、咳やたんには咳止め成分の「ジヒドロコデインリン酸塩」やたんを排出する成分の「アンブロキソール塩酸塩」などが配合された市販薬が適しています。
鼻症状には、眠気が少ない抗ヒスタミン成分「dークロルフェニラミンマレイン酸塩」が配合された市販薬を利用すると良いでしょう。ご自身の症状に合った薬を選びたい場合は、お気軽に薬剤師や登録販売者などの専門家にご相談ください。
(2) 下痢、嘔吐などの胃腸症状の市販薬の選び方
下痢や嘔吐は、ウイルスなどの有害なものを体外に出そうとする反応です。そのため、下痢止め薬などをむやみに服用することはおすすめ出来ません。下痢や嘔吐を和らげたい場合は、善玉菌を増やしてくれる整腸薬や、余分な水分を取り除く「胃苓湯」といった漢方薬などを利用すると良いでしょう。
冬は感染症が増加しやすい季節ですが、手洗いやマスク着用の徹底、十分な睡眠、栄養補給などの予防策を行い、感染リスクを減らすことを心がけましょう。また、症状が出た場合は早めに対処し、体調を整えて、元気に冬を乗り越えましょう。
参考資料
ドラッグインフォメーショングループ
2024.12.01